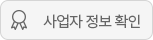-
-
清州市韓国工芸館では、漆企画展を通じて漆の長い歴史とともに発展してきた暮らしに有用な美しさについて語り、 漆工芸の様々な面を見てみようと思います。
その間 2023-11-21 ~ 2024-01-14 場所 清州市韓国工芸館ギャラリー3 主催 清州市 主管 清州市文化産業振興財団、清州市韓国工芸館 作家 Kim Seongho, National Intangible Heritage Center, Kang Woorim, Kim Soomi, Noh Kyeongjoo, Jung Eunjin, Kim Ok, Park Seoungyeol, Lyu Namg won, Huh Myounguk
![]() 商品説明 音声のご案内
商品説明 音声のご案内

清州市韓国工芸館では、漆企画展を通じて漆の長い歴史とともに発展してきた暮らしに有用な美しさについて語り、
漆工芸の様々な面を見てみようと思います。
タイトルの通り、今回の展示のキーワードは「漆黒」です。 計り知れない闇を指して"漆黒のようだ"という言葉を言います。
漆のように黒く光沢があることを意味する「漆黒」という言葉を通じて、私たちの日常の中に漆の文化がどれほど深く染み込んでいるかを確認することができます。
韓国は紀元前3世紀頃、青銅器時代から漆が始まってきたといわれています。 実際、三国史記や朝鮮王朝実録にも漆器を作るため 良い漆を採取するための努力が見られ、全国に数多くの漆の栽培や漆器製作に関連した地名でも韓国の古い漆文化を 確認することができます。 我々が使用する言語や地名まで、大きな影響を及ぼしている漆文化が、2,000年余りの間、我々のそばに残っている理由は何でしょうか?
おそらく伝統的な理由は漆の効能のためだったのでしょう。 木や金属に塗ると、汚れや錆がつかず熱にも強いため、天然仕上げ材であり接着剤として使われてきた、 薬材や食べ物まで、漆は私たちの生活の多くの部分に役立ってきました。 そして長い年月が経った今の私たちは「エコ」というイシューの中で 漆工芸にスポットを当て、その中に現代的な美感を見いだします。
今回の展示は、伝統から同時代までの漆工芸の長い呼吸を見せるために、9人の作家、そして国立無形遺産院とともに3つのパートで構成されています。
最初のパートは、「漆黒から」では、国立無形遺産院の伝承工芸品と忠清北道無形文化財第27号の漆匠、キム·ソンホの作品をご紹介します。 黒い漆をもとに 華やかに輝く螺鈿が目立つ箱と胡足盤、部屋や床の壁にかけて手紙や紙を保管していた峠から馬の鞍まで、漆の様々な用途と 長い間、漆器文化を守ってきた職人たちの努力を垣間見ることができるでしょう。 二つ目は、様々な材料の上に漆の変奏、「ほのかな光から」です。
このパートでは、カン·ウリム、キム·スミ、ノ·ギョンジュ、チョン·ウンジンの4人の作家を通じて、木、陶磁、金属、ガラスと調和する現代の漆を披露します。 また、今回のパートでは 私たちには馴染みのない「金次」という工芸技法に出会うことができます。 割れた陶磁に生漆で結合した後、金粉や銀粉などで装飾する工芸技法である「金次」により 漆工芸のさらなる拡張をお見せしたいと思います。 最後のパート「堅牢さから」、これから数百回の漆が作り出す時間の重さを見てみる番です。
漆は千年を生きるという言葉があります。 それだけしっかりしているということです。 その堅固さの裏には作家の行為があります。 このパートで紹介する4人の作家、キム·オク、 パク·ソンヨル、ユ·ナムグォン、ホ·ミョンウクはそれぞれ異なる方法で工芸を越えて暮らしを実践する材料としての漆を見せてくれます。
漆はウルシの樹液を塗ることを言います。 他の工芸分野と違って、陶磁、ガラス、金属のような材料であるだけでなく、それ自体が技法であり 作家の行為です。 そのため、漆工芸は積み重ねていく漆の厚さほど積み重なっていく「時間性」を示す芸術でもあります。 2,000年という歳月を守ってきた 漆工芸は多くの人々の絶え間ない行為が続き、漆黒のような闇に耐えてきたのかもしれません。 今回の清州市韓国工芸館漆企画展「漆黒から」を通じて 漆工芸が続いてきた時間、深みのある流れをお楽しみください。

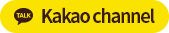
 カスタマーサポート
カスタマーサポート 業務時間
業務時間 入金口座
入金口座